どんなラーメンにも彩りを添える絶品なると巻きのレシピ
熱々のShoyu Ramenをすすっていると、茶系の具材ばかりの丼の中に、真っ白な雲のようなかまぼこにピンクの渦巻きがくっきり映える一片が浮かんでいるのに気づくことがあります。それこそがナルトマキ——つまり、日本生まれの魚肉練り製品のひとつです。

なると巻きとは
ひと言でいうと、なると巻きは白いかまぼこの中にピンクの渦巻きを描いた日本の魚肉練り製品です。白い部分は、細かく砕いた魚を水で丁寧に洗い、砂糖と合わせた「すり身」から作られます。
しっかり水洗いすることで魚特有の生臭さがほとんどなく、上品な味わいに仕上がります。日本におけるすり身産業は規模が大きく、世界の漁獲量のおよそ2〜3%がこの製造工程に充てられているほどです。
使用される魚は、タラやヘイクのような脂肪分の少ない白身魚のフィレが主流です。これは、韓国のオムク(魚の練り物)と同様です。
砂糖(さらにみりんを加えることも)を混ぜるのは、日持ちを良くするため。これは冷蔵庫のなかった時代から受け継がれる知恵です。味付けを終えたすり身は丸太状に整え、蒸して仕上げます。
さらに、中心部分のすり身に赤やピンクの食用色素を混ぜ込むことで、あの愛らしい渦巻き模様が生まれます。

その名前を聞くと人気アニメ『NARUTO -ナルト-』を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、なると巻きの語源は鳴門海峡にあります。淡路島と四国の間に位置するこの海峡は、激しい潮流が生み出す渦潮で有名。なると巻きのピンクの渦は、その自然の造形美を模したものなのです。
なると巻きの歴史
なると巻きのルーツを探るには、日本における魚肉練り製品の歴史をひも解くと面白い発見があります。記録によれば、魚の練り物は平安時代(794〜1192)にはすでに食されており、竹串に刺して炙ったものが、現在の竹輪の原型とされています。
なると巻き自体が世に現れるのは、さらに時代を下った16世紀。江戸期の料理本『蒟蒻百珍』には、当時のなると巻きが昆布や湯葉で包まれていたと記されています。
いまやラーメンの象徴ともいえるなると巻きですが、もともとはそばやうどんの具材でした。ラーメンが広く愛されるようになると、そば職人の一部がラーメンの世界へと活躍の場を移し、その際に持ち込んだのがなると巻きだったのです。

すでに触れたように、醤油ラーメンの主役であるチャーシュー、メンマ(筍)、スープのベースとなるだしなどは、いずれも茶系の色味が中心です。
そこで白とピンクのコントラストが映えるなると巻きが、丼に華やぎを添える存在として重宝されたわけです。とはいえ、近年は豚骨ベースのラーメンが主流となり、醤油ラーメンの比率が減少。それに伴い、なると巻きをトッピングに選ぶ店や客も少しずつ減ってきています。
なると巻きとかまぼこはどう違う?
端的に言えば、なると巻きはかまぼこの一種ですが、かまぼこがすべてなると巻きというわけではありません。かまぼこにはさまざまな形状があり、もっともポピュラーなのは紅白の板かまぼこです。
紅かまぼこは外側がピンクで内側が白、白かまぼこは名のとおり全体が純白。また、筒状で芯が空洞の竹輪もかまぼこの仲間で、香ばしい焼き目が特徴。おでんや天ぷらでおなじみです。
さらに、魚のすり身にカニエキスを加えて作るカニカマは、棒状に成形され、海苔で巻いて寿司ロールに使われることもしばしば。
まとめると、なると巻きは赤〜ピンクの渦巻き模様がトレードマークの、かまぼこの中でも特定のスタイルを指します。

指示
- 深めの鍋に2〜3cmほど水を張って沸騰させ、上に蒸し器をセットする。
- すり身を手作りする場合は、まず魚を下ごしらえする。切り身から皮・脂・骨を取り除き、冷水でさっと洗ってザルにあげ、キッチンペーパーで水気をしっかり拭き取る。200 g 魚の切り身

- 魚をざく切りにする

- フードプロセッサーのボウルに入れる。市販のすり身を使う場合はそのまま加える。卵白、塩、こしょう、砂糖、みりんを加え、なめらかなペーストになるまで回す。1 小さじ 塩, 1 小さじ こしょう, 1 卵白, 1 小さじ 砂糖, 1 小さじ みりん

- ペーストの半量を別の小ボウルに取り、食用ピンク色素を少しずつ加えて鮮やかなピンク色になるまで混ぜる。食用ピンク色素

- 作業台にラップを広げ、白い生地の半量をスパチュラで長方形に薄く伸ばす。

- 白い生地の上にピンクの生地を重ね、長辺に沿って1cmほど縁を残す。

- 巻きすを使い、ペーストをきつめに巻いて円筒形に整える。

- 蒸し器に入れ、約15分蒸す。



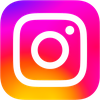
自家製でなると巻きを作れるなんて感動です、ラーメンにのせたら見た目も気分も一気にほっこりして究極のコンフォートフードになりますね。雨の日に熱々のスープと一緒に食べたら、じんわり癒やされそうです☺️
白身魚ベースで脂っこくなく、たんぱく質もしっかり摂れるので見た目以上にバランスが良いのが嬉しいです😊 蒸すだけでこんなにふわっと上品な味になるなんて、ラーメンにも罪悪感少なめで最高でした。
この自家製なると巻き、もう3〜4回作っていますが毎回きれいに渦が出て、ラーメンやうどんが一気に華やいで大満足です😊
魚の練り物が苦手でいつも避ける夫が、この自家製なると巻きは「臭みがなくてふわっとしてる」と言ってラーメンに追加までしていてびっくりしました😊